愛知県陶磁美術館へ行ってきました!
名古屋駅から地下鉄東山線に乗って、
最終駅の[藤が丘]下車。
[藤が丘]からリニモに乗り継ぎ、
[陶磁資料館南]で下車。

リニモの陶磁資料館南で下車し、歩くこと15分くらい。
なんだか裏側から入ったことに徐々に気付きました^^;
とっても広い敷地に3つほどに建物が分かれてまして、
一番最後に回りそうな資料館に最初にたどり着き、
お客さん私たちだけ?っていう雰囲気の中、恐るおそる拝観しました。
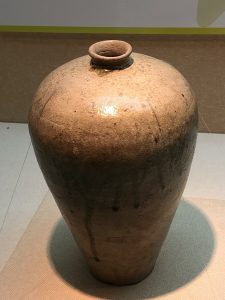
時代をさかのぼった、愛知県内で発掘されたもの、
県内の焼き物の展示でした。
茶器で有名な常滑焼など、
愛知県がいかに窯業が盛んかということがわかります!
次に本館に移動。。
本館は400mくらい離れたところにあり、
そこではやっと10名ほどの人影が見え、
ほっと一安心。
開館40周年ということで「湯呑茶碗」のコレクションが展示されてました。
コレクションは撮影禁止のため、写真はないですが、
全国の絵柄や独特の釉薬が施してある、
見ごたえある湯のみのコレクションでした。
本館の常設展示は圧巻の文化財オンパレード。
縄文時代から鎌倉、平安、江戸時代それぞれ眺めてるだけでは
興奮収まり切れないような、触って触れたい展示品ばかりでした。
黒織部の向付
【黒織部】
銅緑釉のかわりに黒釉をかけたもの。余白の部分には鉄絵。
これはやっぱり作ってみたくなる作品ですね!
シンプルそして大胆な鉄絵。
どんな人が作ったんだろうな?
若手かな?おっちゃんかな?

時代は前後して縄文、弥生時代
薄つくりの高杯

こちらも弥生時代かな
ベンガラの朱色が残るワイングラス形高杯!

薄作りが見事!
エッジの返しも素晴らしい!

織部足つき向付け
千鳥模様が愛らしい。

「鉄絵馬の目皿」 (江戸時代後期)

カニ模様が大好きなワタクシにはたまらない一品。
練りこみで作られてます

圧巻の縄文土器!!
どなたが作ったんでしょうね?
どこでもドアで作っているところを覗いてみたい!^^

【鳴海織部】
白土と赤土を組み合わせ、白土に緑釉をかけ、赤土の箇所には文様を描く。
美しい~!

志野の抹茶茶碗
【志野焼】
長石を釉薬に用い、半透明の乳白色の釉で白磁に似た
白いやわらかな焼きあがり。
下地に鉄絵を施す

分厚いどっしりした感触。
これで抹茶いただいたらこの上ないでしょうなー♬

時代前後して須恵器
弥生時代に比べたら、焼成温度が高くなってきてますね。
福岡にも須恵町というところがあります。
志野 土瓶
無骨豪快!
こちらは現代に近いと思われますが、野性味溢れてます。

織部向付け
その昔どうやって型物を作っていたんだろう?

こちらも織部向付け
この斬新なデザイン!

窯跡からの発掘品も沢山展示してありました。
破片がまた魅力的!

織部向付け
断片だけでも絵になります。

最後はもう一つの狛犬コレクションが展示してある別館へ。
なかなかの百面相!
ユーモラスで最後にひと笑いできました!
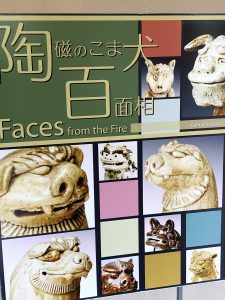
陶器は作った人の思いや心情みたいなものが、
表現できやすい素材なのかなと感じました。
どことなく素朴であったり、洗練されてないところもまた愛着があったり、
おおらかな気持ちにもなれたり、
生活を潤す素材になりうると再認識しました。
時代をさかのぼってみることで、
「食」という基本的な生活の営みの中で、
人との関りがとても大きく、そういう「生活の視点」から
見つめなおしてみるのも面白い材料だなと思いました。
何事も美しいものを観ることは、心の栄養にもなりますね☆
皆さんも機会がありましたら是非訪れてみてくださいね!
